「就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)
就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?
 質問
質問
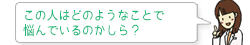
就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?
現在、病院に勤めているものです。退職しようと考えているのですが就業規則に「3ヶ月前に申し出ること」との記載があるのを発見しました。この場合、例えば1ヶ月前に申し出て、就業規則を守らずに退職した場合、損害賠償等のトラブルに発展することはあるのでしょうか。 2016年6月10日
2016年6月10日  15455
15455
 AIによる要約
AIによる要約
 マンガでわかる
マンガでわかる

 イラスト・図解でわかる
イラスト・図解でわかる

 みんなの回答一覧
みんなの回答一覧
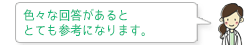
- 1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。 ベストアンサー
-
転職経験がない方ですか?
1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。ただし、退職時に器物を壊したりするなどの特別なアクシデントがあった時は別ですよ。就業規則に3ヶ月と書かれていても、それは無効です。典型的な雇用側の脅し文句ですね。いわゆるブラック病院です。まあ、看護師さんなどは人手不足感が強いので、あの手この手で辞めさせないようにしているみたいですね。
退職は転職だけではなく、介護や病気、配偶者の転勤など色々な理由があります。3ヶ月も拘束なんてされたら困っちゃいますよ。
法律では2週間前に申し出をすれば良いとなっていますが、1ヶ月前が妥当との判例もありますので、1ヶ月前に退職の申し出をして、退職をすれば何も問題ありません。
 2016年6月23日
2016年6月23日
役に立った(6)
- トラブル等に発展することはないと思います ベターアンサー
-
病院側も退職の直前で言われて、急に採用をして人を補わなければならなくなったら大変なのでそういった就業規則を設けているのでしょう。
1ヶ月前に申し出たとしても特に損害賠償等を請求されるといったことはないと思いますよ。ただ、転職されるのであれば、状況をよくみて、早めに退職の意思をお伝えになった方がすっきり辞められると思います。
「立つ鳥跡を濁さず」ということわざのごとく、周囲の人にとっても自分にとっても一番いい形で退職できるといいですね。
 2017年2月22日
2017年2月22日
役に立った(2)
- あわせて以下もご参考にしてください。 公式
-
<類似の質問>
https://crc-bank.com/keijiban?gu=61
(会社規定で在職中の転職活動を禁止されていますが、次の転職先を決めてから退職するべき?)
https://crc-bank.com/keijiban?gu=143
(退職の申し出をしてからCRCへの転職活動を始めるべきでしょうか)
https://crc-bank.com/keijiban?gu=174
(在職中から転職活動をしても良いでしょうか?在職中と離職中では合格率に差はありますか?)
https://crc-bank.com/keijiban?gu=38
(治験コーディネーターへの転職活動を始めるタイミングはいつでしょうか?)
<類似の転職成功事例>
https://crc-bank.com/seikoujireinum?num=23
(強い退職引き止めにあいながらも粘り強く転職活動をした結果、治験コーディネーターへ転職成功)
<類似の記事>
https://crc-bank.com/taisyokutetsuzuki
(治験コーディネーターの退職手続き)
https://crc-bank.com/crcnoqa#qa26
(在職中だけど大丈夫?)
https://crc-bank.com/crcnoqa#b882
(ブランクがあります。治験コーディネーターへ転職できますか?)
 2021年1月21日
2021年1月21日
- 就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか? AI
-
就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになる可能性はありますが、ケースによって異なります。一般的には、以下のような場合に損害賠償請求をされるリスクが高まります。
・有期雇用で期間内に一方的に退職してしまった場合
・引き継ぎをせず退職した場合
・退職するとき、他の従業員に転職の勧誘や引き抜きをした場合
ただし、損害賠償請求をされても、必ずしも支払わなければならないわけではありません。会社側が損害の発生とその額を証明しなければならないからです。
期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の従業員は、法律上、就業規則に「退職は3ヵ月前に申し出ること」と書いてあっても、退職を申し出てから2週間経過することで退職可能です。ただし、期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)であれば、この就業規則が適用される場合があります。
就業規則に従わずに退職すると、場合によっては損害賠償等のトラブルになる可能性があります。例えば、従業員が急に退職して仕事を放棄したことにより、会社の売上に影響が出てしまった場合は、損害賠償に発展してしまう可能性があります。ただし、適法に退職できた場合には、法律上は、損害賠償責任を負うことはありません。
医療機関では後任の確保や引き継ぎに時間がかかるため、一般的には退職希望日の半年前から最低でも3ヶ月前には辞意を伝えることが望ましいとされています。退職する際は、職場や患者さんへの配慮も忘れないようにしてください。
※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから
- 就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか? AI
-
就業規則を守らずに退職した場合の損害賠償等のトラブルについて、以下に詳しく説明します。
原則:就業規則は法的拘束力を持つが、退職の自由は保障されている
就業規則は、労働基準法に基づいて作成・届け出が義務付けられており、一定の法的拘束力を持ちます。従業員は就業規則を遵守する義務があります。しかし、同時に、民法では退職の自由が保障されており、労働者は原則としていつでも退職することができます(民法第627条)。
「3ヶ月前申告」の規定について
就業規則に「3ヶ月前に申し出ること」と定められている場合でも、これはあくまでも会社と従業員間の取り決めです。民法では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば退職できるとされています。そのため、法的には、1ヶ月前に申し出たとしても、2週間後には退職することが可能です。
損害賠償等のトラブルについて
就業規則に違反して退職した場合、会社から損害賠償を請求される可能性は理論上はありますが、実際に請求が認められるケースは非常に限られています。会社が損害賠償を請求するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
◆ 従業員の退職によって会社に具体的な損害が発生したこと
◆ 損害と退職との間に因果関係があること
◆ 損害額を具体的に立証できること
例えば、従業員の突然の退職によって代替要員の確保が間に合わず、事業に重大な支障が出た場合などに、損害賠償が認められる可能性があります。しかし、通常の退職であれば、会社は代替要員を確保するなどの対応を取ることが一般的であり、損害賠償請求が認められるケースは稀です。
病院の場合の注意点
病院の場合、患者の生命や健康に関わる業務であるため、人員配置が非常に重要です。そのため、急な退職は病院運営に影響を与える可能性があります。円満退職のためには、できる限り就業規則に沿って3ヶ月前に申し出るのが望ましいですが、事情によっては、上司とよく相談し、引継ぎなどをしっかりと行うことで、トラブルを避けることができるでしょう。
まとめ
就業規則の「3ヶ月前申告」は努力目標と考え、できる限り守るように努めることが望ましいです。しかし、法的には2週間前に申し出れば退職できます。損害賠償請求のリスクは非常に低いですが、円満退職のためには、上司とよく相談し、誠意をもって対応することが大切です。
項目 説明 民法第627条 民法第627条第1項には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められています。つまり、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職の意思表示から2週間で退職が成立します。 就業規則の効力 就業規則は、会社と従業員の間の労働条件を定めた規則ですが、法律(民法)に反する内容を定めることはできません。そのため、就業規則に「3ヶ月前に申し出ること」と記載されていても、民法の規定が優先され、2週間で退職することが可能です。 3ヶ月前告知の法的拘束力 就業規則の「3ヶ月前告知」は、あくまでも会社から従業員へのお願いであり、法的拘束力はありません。従業員は、就業規則に従って3ヶ月前に申し出ることもできますが、民法の規定通り2週間後に退職することもできます。 損害賠償請求の可能性 基本的には、2週間前に退職の意思表示をしていれば、会社から損害賠償を請求されることはありません。ただし、以下のような特殊なケースでは、損害賠償請求が認められる可能性もゼロではありません。 損害賠償が認められる可能性のあるケース ◆業務の引継ぎを全く行わなかった場合: 後任者への引継ぎを全く行わず、会社に大きな損害を与えた場合。ただし、損害賠償が認められるためには、会社側が具体的な損害額を立証する必要があります。
◆重要なプロジェクトの途中で、代替要員が確保できない状況で退職した場合: プロジェクトの進行に重大な支障が生じ、会社に大きな損害を与えた場合。これも、会社側が具体的な損害額を立証する必要があります。
◆退職によって会社が倒産した場合: 極めて稀なケースですが、従業員の退職によって会社が倒産するなど、通常では考えられないような重大な損害が発生した場合。退職時の対応 トラブルを避けるためには、できる限り就業規則に沿って早めに退職の意思を伝えることが望ましいです。引継ぎなども丁寧に行い、円満退職を目指しましょう。もし、どうしても就業規則の期間を守れない場合は、その理由を会社に説明し、理解を求めることが大切です。 まとめ 就業規則に「3ヶ月前に申し出ること」と記載されていても、民法に基づき2週間で退職可能です。通常の場合、就業規則を守らなかったとしても損害賠償等のトラブルに発展することはありません。しかし、業務の引継ぎを全く行わないなど、会社に著しい損害を与えた場合は、損害賠償請求のリスクもゼロではありません。円満退職のため、できる限りの配慮を心がけましょう。
※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから



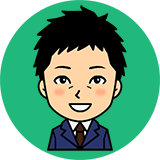

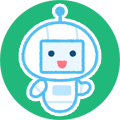


 年収査定はこちら
年収査定はこちら
 合格予想はこちら
合格予想はこちら
 掲示板で質問をする
掲示板で質問をする






 CRC
CRC

 CRCの
CRCの
 CRCの
CRCの
 CRCの
CRCの
 CRCの
CRCの
 CRCに
CRCに
 CRCの
CRCの
 SMO
SMO
 SMO
SMO
 応募先の
応募先の
 治験
治験
 院内CRCと
院内CRCと



 2026年4月からの転職
2026年4月からの転職 CRC未経験特集
CRC未経験特集 CRC経験者特集
CRC経験者特集 看護師特集
看護師特集 臨床検査技師特集
臨床検査技師特集 保健師特集
保健師特集 薬剤師特集
薬剤師特集 管理栄養士特集
管理栄養士特集 臨床工学技士特集
臨床工学技士特集 理学療法士特集
理学療法士特集 作業療法士特集
作業療法士特集 臨床心理士特集
臨床心理士特集 MR特集
MR特集 CRA経験者特集
CRA経験者特集





 求人検索
求人検索  ログイン
ログイン 会員さま専用
会員さま専用 CRCの仕事
CRCの仕事  治験業界の研究
治験業界の研究 経験・資格別の注意点
経験・資格別の注意点 応募書類の作成
応募書類の作成 面接・適性検査の対策
面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ
みんなのクチコミ みんなの質問と回答
みんなの質問と回答 転職成功事例
転職成功事例 マンガで分かるCRC
マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル
CRCばんくチャンネル 便利な機能
便利な機能 相談/年収査定/合格予想
相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?
2026年から働くには? 退職手続き
退職手続き 開催中のキャンペーン
開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは
《CRCばんく》とは